コースデザイン概要
学習者の目標達成のために誰が、何を、どのように教え、どう評価するのかを決めて授業の計画をたてること
・ニーズ調査
学習者の背景(年齢、母語、目的、学習経験)を調べる
学習目的(進学、日本での生活、仕事など)を把握
・レディネス調査
〇外的要因
・年齢、職業、国籍、母語
・経済的条件(学習者にお金をどれくらいかけられるか)
・時間的条件(学習者にかけられる時間がどれくらいあるか)
・生活状況(アルバイトをしている、家が遠い家族の世話の必要があるなど)
〇内的要因
・これまでの日本語学習について(どんな教科書を使って勉強した、どれくらいの期間勉強した、どんなふうに勉強したなど)
・その他の外国語の学習について(日本語以外に外国語を勉強したことがあれば外国語の独自の方法論がわかっている場合が多い)
・学習スタイル(講義形式が好き、やりとりが好き、復習が好き、宿題が好き、書いて覚える、発音して覚えるなど)
・目標言語調査
どんな日本語を理解・使用できなければならないかを調査
・言語使用調査
学習者がどんな日本語を使っているかを調査
・コース目標
ニーズとレディネスを踏まえコースの目標を決める。
国際交流基金が日本語教育のための枠組みとしてJF日本語教育スタンダードを発表。JF日本語教育スタンダードではCEFRを基にした評価基準を採用。CEFRは「CAN-DO~ができる」という言語活動を評価基準にしている。
・シラバスデザイン
シラバスとは教授項目のこと。「何を教えるか」その要素を一覧にしたもの。どんな教授項目を教えるかを確定すること=シラバスデザイン。
・構造シラバス→文法、文型、語彙といった文法系の理解が進むように考えて集められたシラバス。「みんなの日本語」は構造シラバス。教授法でいうとオーディオリンガルメソッドは構造シラバス。
・場面シラバス→スーパーで買い物をする、乗り物に乗る、レストランで外食をするのようなコミュニケーションが必要な場面での表現や語彙などを集めたシラバス。勉強した後すぐに使えるため来日直後や短期滞在者に向いている。目次が場面で書かれている。「できる日本語」では目次は「買い物」「友達の家で」「バスツアー」などの「場面」で書かれている
・機能シラバス→依頼、同意、提案など言語の持つ機能に着目し分類したシラバス。教授法でいうとコミュニカティブアプローチは機能シラバスを中心にしている。基本的な文法項目をすべて組み込むことが難しく文法を体系的に学ぶのには向いてない。
・話題シラバス(トピックシラバス)→学習者の必要な話題や興味のある話題に関する文型、文法、語彙を集めたシラバス。中上級の読解に向いているシラバスで「上級のとびら」という中級向け教科書は話題シラバスで目次が話題=トピックで書かれている。「日本の地理、日本のポップカルチャー、日本の教育」というような話題=トピックがならんでいる。
・技能シラバス(スキルシラバス)→「聞く、話す、読む、書く」の4技能それぞれの熟達を目指すシラバス。技能の習熟によってより高度なことができるようになることを目指す。中上級の副教材として使われることが多い。
・課題シラバス(タスクシラバス)→ある課題(タスク)を達成することを目指すシラバス。タスクを達成するにはコミュニケーションが必要。タスク達成のためのコミュニケーションを通して目標言語を学ぶことができる。「旅行を計画する」「デートに誘う」「パーティーを企画する」など。ピア活動との相性も良い。教授法で言うとタスク中心の教授法が課題シラバスにあたる
学習者のニーズ・レディネスに合わせてバランスよくシラバスの要素を組み合わせると良い。複数のシラバスを組み合わせえたものを「複合シラバス」という
先行シラバス→あらかじめ決まっているシラバス
後行シラバス→授業が終わったあとに結果的に教えたシラバス。カラン提唱コミュニティ・ランゲージ・ラーニング(CLL)
プロセスシラバス→先行シラバスと後行シラバスの中間的な存在で事前にある程度は決めておくが授業の進度によっては途中で加えるシラバス。
・カリキュラムデザイン
シラバスをいつ、どれくらい教えるのか時間の流れと量のバランスを考慮したもの。全体の期間を考慮した計画。シラバスを量的、時間的、時系列で考え計画すること。=カリキュラムデザイン
教授法・教材・活動の選択
教科書の活用+補助教材(ニュース、絵本、動画など)
学習者のニーズ・レディネスに合わせて意欲を高め効率よく習得できるようちょうどよいバランスの教授法、教材を考える。
タスク中心アプローチや協同学習の導入
授業実施、テストの実施
学習者の評価とフィードバック
アチーブメントテスト(到達度テスト)
プロフィシェンシーテスト(能力テスト)
形性的評価と総括的評価
「真正性」や「有用性」の観点
個別指導や相談の実施
実施した授業や内容に対する評価
P→D→C→A 「PDCAサイクル」


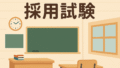
コメント